Inspiration_Notes|{{ 2025-05-14 }}
ラジオニュース|「若者の宗教離れ」の話を聞いて。
現代の宗教離れの背景には、社会の変化があります。
かつて人々は、「無限の自由」に不安を感じていました。
そこで宗教が与える「制限のある自由」は、秩序と安心をもたらし、生き方の指針として受け入れられていたのです。
しかし現代社会では、法律やマナー、社会的規範といったルールがあふれ、すでに私たちは多くの「制限の中」で暮らしています。
このような状況では、宗教によるさらなる束縛は必要とされなくなってきているのかもしれません。
たとえるなら、
「砂漠」は自由すぎて過酷であり、
「森」はほどよい秩序の中で居心地がよく、
「密林」はルールが多すぎて息苦しい場所。
現代社会は、ちょうどこの「密林」に近い状態にあるのかもしれません。
「人間は本来、森のようなシンプルな秩序の中で、直感に任せて快適に生きるのが理想的だった。
しかし現代は、判断を強いられる密林であり、思考資源を浪費し続ける環境に変わってしまった。」
「現在は自分が男か女なのかさえ脳を浪費して考えねばならない。」


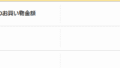
コメント