執着=バイアス?
仏教でいう「執着」は、行動経済学における「認知バイアス」と構造が似ています。
とくに以下のようなバイアスは、まさに執着です。
- 損失回避バイアス(失うことを極端に恐れる)
- 保有効果(自分の持っているものを過大評価する)
- 現状維持バイアス(変化を嫌う)
私たちはこうしたバイアスにより「本当の選択」から目を背けてしまいます。
“死”によって“生”が見える
トルストイの『イワン・イリイチの死』や黒澤明の映画『生きる』では、
「死の宣告」が人生の目覚めをもたらします。
それまでバイアス(執着)に支配されていた主人公は、死を前にしてようやく
「本当に大切なもの」に気づくのです。
これは「象徴的な死」=古い自己の脱却とも言えます。
侍が剣を捨てたように、執着を捨てた者が生き残る
明治維新後、剣(=誇りや過去の価値観)に執着した侍たちは時代に取り残されました。
一方で、執着を捨てて商い・教育・国家建設へ進んだ者たちは、新時代を切り開きました。
これは現代にも通じる、「執着を捨てた者が生き延びる」という普遍的な教訓です。
ナッジ:バイアスをやさしくコントロールする方法
ナッジ(nudge)とは、人の選択を“強制せずに”導く設計のこと。
仏教的に言えば「善い縁をつくる」ことで、執着を手放す環境を整える手段とも言えます。
例:
- 野菜を食べやすくするために目立つ場所に置く
- 電気代の請求書に「ご近所より使いすぎ」と表示
- 自動的に貯金される仕組みを設定する
まとめ:死と執着と、生の発見
- 執着は心の錯覚=バイアスである
- “死”という強烈な揺さぶりによって、執着が崩れ、本当の生が見える
- 剣を捨てた侍のように、執着を手放した者こそが新しい世界を生き抜く
- ナッジのように「やさしく手放せる環境づくり」も大切
一言で言えば…
「執着とは、心の錯覚。死はそれを照らす光。手放すことで人は本当に生き始める。」
関連記事アイデア
- 「ナッジ」と仏教:やさしい悟りの設計とは?
- 『イワン・イリイチの死』と『生きる』の比較考察
- 剣を捨てた侍たちと、現代人の自己変革
最後まで読んでくださってありがとうございます。

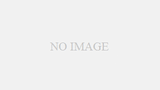
コメント